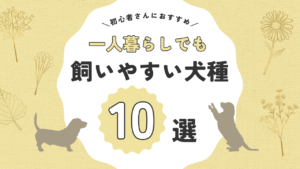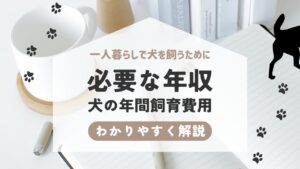一人暮らしで犬を飼いたいけど、お金っていくらかかるんだろう?
この記事では、一人暮らしで犬を飼いたいけど、お金がいくらかかるのかわからない方に向けて、必要な初期費用の目安や準備するもの、節約のヒントについてわかりやすく解説します!
- 初期費用の内訳と金額の目安
- 入手方法による費用の違い
- 初期費用を節約するヒント
さっそく、一人暮らしで犬を飼うために必要な「初期費用」について解説します。


一人暮らしで犬を迎えるために必要な初期費用
初期費用っていくら必要なの?
犬の入手方法などによって大きく変わりますが、おおよそ5万円〜57万円が目安です。
一般的な初期費用の内訳を見てみましょう。
| 項目 | 金額の目安 | 備考 |
|---|---|---|
| 生体購入 | 0〜50万円程度 | 入手方法で異なる |
| 飼育グッズ | 3万~4万円前後 | フード、トイレ用品など |
| 畜犬登録 | 約3千円程度 | 義務がある |
| 狂犬病 ワクチン接種 | 約3千~4千円 | 接種義務がある |
| 混合ワクチン | 1回あたり 約5千~1万2千円 | 種類で異なる |
| マイクロチップ 装着・登録 | 約3千~1万円 | 義務がある※ |
| 初期費用の合計 | 約4万4千〜56万7千円 | ー |
初期費用は、「譲渡を受ける」のか「購入する」のかによって、大きく異なります。
「畜犬登録」「マイクロチップ装着」「狂犬病ワクチン接種」などは、法律で義務づけられているため外せません。
生体購入費


犬の入手方法は、大きく分けて「譲渡」と「購入」の2つに分けられ、生体購入に必要な費用が大きく異なります。
| 入手方法 | 譲渡 | 購入 |
|---|---|---|
| 入手場所 | ・動物愛護センター ・保護団体 | ・ペットショップ ・ブリーダー |
| 価格相場 | 無料〜60,000円程度 | 約100,000〜600,000円 |
| 条件 | 条件あり | なし |
| 初期費用の目安 | 約33,000〜115,000円 | 約100,000〜610,000円 |
どこから犬を入手するのが正解ということはないので、「あなたの暮らし方に合った選択肢」を見つける参考にしてください。
保護犬を迎える場合


保護犬を迎える際の初期費用の目安は、以下のとおりです。
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 譲渡費用 | 0〜60,000円程度 |
| 登録料 | 約3,000〜5,000円程度 |
| 飼育グッズ | 約30,000〜50,000円程度 |
| 合計 | 約33,000〜115,000円程度 |
保護犬を迎える場合、基本的に譲渡費用は無料のため、初期費用をぐっと抑えることができます。
治療費や避妊・去勢手術などにかかった初期医療費のみの負担になるケースが多いです。
「動物愛護活動に貢献したい」「初期費用を節約したい」という人におすすめの方法です。
ただし、譲渡を受けるためには応募条件や審査があるため、事前によく確認したうえで申し込みましょう。
保護犬の譲渡について詳しくは、下記の記事をご覧ください。


ブリーダーから購入する場合


ブリーダーから購入する際の初期費用の目安は、以下のとおりです。
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 生体購入費 | 約50,000〜300,000円程度 |
| 登録・医療費 | 約20,000〜30,000円程度 |
| 飼育グッズ | 約30,000〜50,000円程度 |
| 合計 | 約100,000〜380,000円程度 |
ブリーダーから直接購入するため、中間費用がかからず、ペットショップより低価格で購入できる可能性があります。
「お迎えしたい犬種が決まっている」「ペットショップより安く購入したい」という人におすすめの方法です。
ブリーダーからの購入方法について詳しくは、下記の記事をご覧ください。


ペットショップで購入する場合


ペットショップから購入する際の初期費用の目安は、以下のとおりです。
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 生体購入費 | 約150,000〜500,000円程度 |
| 登録・医療費 | 約25,000〜60,000円程度 |
| 飼育グッズ | 約30,000〜50,000円程度 |
| 合計 | 約205,000〜610,000円程度 |
「店舗で直接見て決めたい」「すぐに犬を迎えたい」という方には、ペットショップがおすすめです。
お店で必要な飼育グッズもまとめて購入できるため、忙しくて時間がない方におすすめの入手場所です。
ただし、可愛い子犬に一目惚れして衝動買いしてしまわないように、注意が必要です。
ペットショップからの購入方法について詳しくは、下記の記事をご覧ください。


飼育グッズ
安心して犬を迎えるために、必要な飼育グッズをあらかじめそろえておく必要があります。
最初にそろえておきたい飼育グッズと一般的な価格帯は、以下のとおりです。
| 項目 | 価格帯 |
|---|---|
| ハウス (ケージ・サークル) | 約5,000〜30,000円 |
| ドッグフード、おやつ | 約6,000〜7,000円 |
| 食器・給水器 | 約500〜20,000円 |
| お散歩グッズ | 約5,000〜10,000円 |
| トイレ用品 | 約3,000〜12,000円 |
| おもちゃ | 約1,000〜2,000円 |
| クレート キャリーバッグ | 約4,000〜15,000円 |
| お手入れグッズ | 約5,000〜20,000円 |
| 滑り止めマット | 約2,000〜10,000円 |
| ペットゲート | 約5,000〜2,0000円 |
| ペットベッド | 約2,000〜10,000円 |
| 合計 | 約38,500〜156,000円 |
ハウス(ケージ・サークル)
犬にとってケージやサークルは、自分だけの安心できる「おうち」です。
お迎え初日から必要になるため、あらかじめ準備しておきましょう。
「ケージ」は、天井や床があり、しっかり囲まれた構造のものを指します。
「サークル」は、側面のみが囲まれていて天井のない柵のことです。
▼デザイン性の高いものや、インテリアに合う木製タイプが人気です。
▼留守番が多い場合は、広めのタイプや天井付きのケージがおすすめです。
サイズ選びが不安な方は、「小型犬用」「大型犬用」などで検索すると、ちょうどよい商品が見つかりやすくなります。
ハウスの種類の選び方や配置については、下記の記事をご参照ください。


ドッグフード、おやつ
毎日食べるものだからこそ、ドッグフードやおやつは質のよいものを選びたいですよね。
【ブラバンソンヌ】、【ペットフードのアカナ・オリジン】、【K9Natural(ケーナインナチュラル)】
我が家では、アレルギーリスクを軽減する獣医師監修のペットフード【ブラバンソンヌ】のオーシャンフィッシュを与えています。
お迎え直後は、引き取り先で与えられていたものと同じフードを用意して与えるのが安心です。
おやつは、トレーニングやごほうび用に用意しましょう。


食器・給水器
ごはん用の食器と給水器は、それぞれ1つずつ用意しましょう。
最初は、引き取り先と同じ(使い慣れた形状)のものを選ぶと安心です。
▼陶器製やステンレス製は重みがあり安定しやすく、お手入れも簡単です。
▼ボトルタイプの給水器は、お水にほこりやゴミが入りにくく衛生的です。
▼最近は「自動給餌器」「自動給水器」や「スタンド付きのボウル」も人気で、食べやすさや飲みやすさに配慮されたデザインが豊富です。
お散歩グッズ
お散歩デビュー前の子犬を迎える場合でも、お散歩に必要な基本セットをあらかじめ準備しておきましょう。
お散歩の基本セット
- 首輪
- ハーネス
- リード
- 給水ボトル
- うんち袋
- お散歩バッグ
首輪やハーネス、リードに慣れさせる練習をしたり、抱っこ散歩のときにも着用が必要です。
▼かわいいデザインのものも多く、選ぶのも楽しいです。
犬の安全に関わる大切なものなので、素材や作りがしっかりしたものを選んで購入しましょう。
トイレ用品
お迎えした日からトイレトレーニングを始められるように、トイレ用品もあらかじめ準備しておきましょう。
ペットシーツは、サイズや吸収力などの機能によって価格が異なります。
最初はトイレトレーニングで多く使うため、多めに用意しておくと安心です。
▼留守番中は、厚手で吸収力のあるものが便利です。
▼トイレトレーは必ずしも必要ではありませんが、いたずら対策や足濡れ防止に、メッシュ付きのタイプがあると便利です。
▼足上げをする男の子用には、側面にシーツを付けられるL字型トレーなどもあります。
おもちゃ
遊びは、犬との大切なコミュニケーションです。
おもちゃは、ストレス解消や知育にもつながります。
▼犬の好みに合わせて、ボールや噛んで遊べるタイプなどを1〜2個用意しましょう。
あとで好きなだけ買ってあげられるので、まずは予算1,000〜2,000円程度にしておくのがおすすめです。
誤飲防止のため、サイズと素材の選定には注意してください。
クレート・キャリーバッグ
旅行や通院、災害時の避難などに使える移動用のクレートやキャリーバッグも用意しておきましょう。
犬が落ち着いて過ごせるよう、ふだんから慣れさせておくと、いざというときに安心です。
クレートやキャリーバッグの選び方については、下記の記事をご参照ください。


お手入れグッズ
犬のお手入れに使うグッズも必要です。
基本的なお手入れグッズ
- ブラシ(スリッカー、コーム)
- ボディ用ウェットシート
- 爪切り
- 耳そうじ用品
- 歯磨き用品
- シャンプー・リンス
犬種によってお手入れの方法は異なります。
必要なものを確認して、準備しておきましょう。
滑り止めマット
フローリングは滑りやすく、犬の関節に負担がかかりやすいため、あらかじめ滑り止めマットを設置しておくことをおすすめします。
▼お粗相などで汚れてしまったときには、洗えるタイプが便利で人気です。
ペットフェンス・ペットゲート
犬が急に外に飛び出したり、危険な場所へ行くのを防ぐために、ペットフェンスやペットゲートを、あらかじめ購入して設置しておきましょう。
ペットベッド
ペットベッドは、実は絶対に必要というグッズではありません。
トイレトレーニングがまだ済んでいない子犬の場合、失敗してベッドを汚してしまう可能性があるほか、犬の性格によっては噛んで壊してしまったり、ふかふかのベッドよりも硬い材質(床やトイレトレー)の上を好むこともあります。
最初は、汚れても洗えるブランケットや、捨ててもよいタオルなどの代用品でも十分です。
トイレの成功率が高くなったタイミングや、寒い季節になってから導入を検討するのがおすすめです。
購入する際は、洗えること、防水加工付きであること、ケージに入るサイズであることがポイントです。
一度にすべてをそろえられない場合は、すぐに必要な最低限のものから準備し、徐々に必要なものを買い足していく方法もおすすめです。
犬の性格や暮らし方に合ったグッズを見つけて、無理のない準備を進めましょう。
一人暮らしで犬を迎えるときにそろえておきたい「飼育グッズ10選」については、以下の記事で詳しくご紹介しています。


登録料・マイクロチップ・医療費など


犬を迎えたら、すぐに必要になるのが登録料や医療費です。
必要な項目と費用の目安は、以下のとおりです。
| 項目 | 費用の目安 |
|---|---|
| 畜犬登録 | 約3,000円 |
| マイクロチップ | 約3,000〜10,000円 |
| 狂犬病ワクチン接種 | 3,000~4,000円程度 |
| 混合ワクチン接種 | 1回あたり約5,000〜12,000円 |
畜犬登録


犬を飼う場合、飼い始めてから30日以内、または生後90日以内の子犬の場合は生後90日を経過してから30日以内に、お住いの市区町村で畜犬登録をする必要があります。
畜犬登録は、日本国内で犬を飼っているすべての人に義務付けられていますので、必ず登録をしましょう(違反した場合は、20万円以下の罰金)。
すでに畜犬登録が済んでいる犬を迎える場合は、所有者の変更届が必要です。
畜犬登録にかかる費用は市区町村によって異なりますが、一般的には以下のとおりです。
| 項目 | 費用の目安 |
|---|---|
| 新規登録手数料 | 1頭につき3,000円程度 |
| 変更届の手数料 | 無料 |
畜犬登録の手続きや費用の詳細は、各自治体の公式ウェブサイトや窓口で確認できます。
畜犬登録に関する詳しい情報は、厚生労働省「犬の鑑札、注射済票について」のページをご確認ください。
マイクロチップ装着


2022年6月以降、法律で犬や猫を販売する前にマイクロチップを装着・登録することが義務付けられています。
動物の愛護及び管理に関する法律(以下「動物愛護管理法」という。)において、ブリーダーやペットショップ等は、犬や猫を販売する前にマイクロチップを装着・登録することが義務付けられています。
引用:「マイクロチップ情報登録制度」総務省
ブリーダーやペットショップ等から犬や猫を購入した飼い主は、所有者の変更登録をして、所有者の情報を自分の情報に変更します。動物愛護団体や知人等から犬や猫を譲り受けた場合にも、装着・登録を行うことが推奨されています。
すでに装着が完了している犬を引き取った場合は、変更届を提出しましょう。
マイクロチップの装着にかかる費用は動物病院によって異なりますが、一般的には以下のとおりです。
| 項目 | 費用の目安 |
|---|---|
| 装着費用 | 約3,000円〜10,000円程度 |
| 登録料 | オンライン:400円 書面:1,400円〜 |
| 変更届の提出費用 | 無料 |
一部の自治体では、ご家庭で飼育している犬のマイクロチップ装着費用に対する補助や助成を行っている所もありますので、確認してみましょう。
マイクロチップ装着に関する詳しい情報は、環境省「犬と猫のマイクロチップ登録情報」のページをご確認ください。
狂犬病ワクチン接種


生後91日以上の犬の所有者には、犬を取得した日(生後90日以内の犬を取得した場合は、生後90日を経過した日)から30日以内に、狂犬病ワクチンを接種させることが法律で義務付けられています。
その後は毎年1回、狂犬病ワクチンの接種が必要です。
違反した場合、20万円以下の罰金が科されます。
狂犬病は、発症すると治療法がなく、ほぼ100%の致死率を持つ感染症です。
感染した動物に咬まれると、人にも感染する可能性があります。
このため、法律で定められた予防接種を受けることが大切です。
一般的に4〜6月ごろに、畜犬登録されている住所宛てに「狂犬病予防注射の通知書」が届きます。
通知書は接種時に必要な書類ですので、届いたら大切に保管し、接種の際に持参しましょう。
狂犬病ワクチンは「動物病院」や「集団接種会場」で接種できます。
動物病院と集団接種会場で接種を受ける際の費用項目の違いは、以下のとおりです。
| 項目 | 動物病院 | 集団接種会場 |
|---|---|---|
| 狂犬病ワクチン接種料 | 3,000~4,000円程度 | 約3,000円 |
| 注射済票交付手数料 | 550円 (※別途代行手数料がかかる場合もある) | 550円 |
| 診察料 | 1,000~2,000円程度 | なし |
| 合計金額 | 約4,500〜6,500円 | 約3,550円 |
集団接種会場の場合は診察料がかからないため、少しでも費用を抑えたい人におすすめです。
また、接種と同時に注射済票の交付や畜犬登録ができる場合も多く、手続きを手軽に済ませたい人にも便利です。
ただし、一般的に4〜6月と開催期間や時間帯が限られているため、スケジュールをしっかり確認しておきましょう。
集団接種会場では獣医師による詳細な診察は行われないため、犬の健康状態や性格に不安がある場合は、動物病院での接種を選ぶといいでしょう。
狂犬病に関する詳しい情報は、厚生労働省「狂犬病」のページをご確認ください。
混合ワクチン


混合ワクチンは、複数の感染症から犬を守るためのワクチンです。
一般的に「5種混合」「6種混合」「8種混合」「10種混合」などがあり、含まれるワクチンの種類が異なります。
成犬の場合、通常年1回の追加接種が推奨されています。
子犬の場合は、母犬からの移行抗体があるため、生後45~60日頃に1回目を接種し、その後2~4週間間隔で2~3回接種するのが一般的です。
具体的な接種スケジュールや適したワクチンの選択については、かかりつけの獣医師にご相談ください。
混合ワクチンの費用は、ワクチンの種類や動物病院によって異なります。
一般的な価格帯は以下のとおりです。
| ワクチンの種類 | 費用の目安 |
|---|---|
| 5種混合ワクチン | 5,000円〜8,000円程度 |
| 6種混合ワクチン | 6,000円〜9,000円程度 |
| 8種混合ワクチン | 7,000円〜10,000円程度 |
| 10種混合ワクチン | 8,000円〜12,000円程度 |
※上記はあくまで目安であり、診察料などが別途発生する場合があります。正確な料金は、接種を検討している動物病院に直接お問い合わせください。
ワクチン接種を受けていない場合は、ドッグランやペットホテルなどの施設利用が制限されることがあります。
犬とレジャーや旅行を楽しみたい方は、事前に接種を済ませておくとよいでしょう。
【実例】私が犬を迎えたときの初期費用の内容


ちなみに、私が実際に支払った初期費用は、約17万5,000円でした。
私はペットショップで、生後7ヶ月でセール価格になっていた子犬を迎えました。
そのときにかかった初期費用は、以下のとおりです。
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 生体購入費用(ワクチン代など込) | 約160,000円 |
| 飼育グッズ代など | 約15,000円 |
| 合計 | 約175,000円 |
飼育グッズは、必要最低限のものだけをそろえて、できるだけ節約を意識しました。
初期費用を節約する3つのポイント


使えるお金に限りがある一人暮らしの場合は、「どこにお金をかけて、どこで工夫するのか?」を見極めて予算計画を立てることが大切です。
ここでは、初期費用を抑える3つの節約ポイントをご紹介します。
保護犬を迎える
初期費用を抑える方法のひとつが、保護犬の譲渡を受けることです。
保護犬とは、保健所や動物愛護団体などで保護され、新しい飼い主を探している犬たちのことです。
購入に比べて費用が抑えられるだけでなく、「命を救う」という意味でも、とても意義のある選択です。
譲渡費用は施設によって異なりますが、治療や去勢・避妊手術などにかかった費用を負担する形になります。
ただし、保護犬を迎える際は、譲渡前の面談や家庭訪問、トライアル期間の設定など、一定の条件を満たし、審査を受ける必要があります。
一人暮らしの場合は、「飼育可能な住環境」や「留守中の管理体制」などを丁寧に説明する必要があります。
条件が合えば、保護犬はとても良いパートナーになります。
予算を抑えつつ、動物愛護活動に貢献したい方におすすめの方法です。


フリマアプリを活用する
犬との暮らしに必要なグッズはたくさんありますが、すべてを新品でそろえる必要はありません。
フリマアプリをうまく活用することで、初期費用を節約することができます。
メルカリなどのフリマアプリでは、未使用品や数回しか使っていないきれいな状態のペット用品が、手頃な価格で出品されていることも多くあります。
\さっそくペット用品を探しに行く/
ただし、中古を使う場合は、消毒・洗浄をしっかり行い、衛生面に注意しましょう。
食器やベッド、ブラシなど、直接体に触れるものは、新品を購入することをおすすめします。
少しずつ買い足す
あれもこれもと、必要以上にいろいろと買いすぎてしまうのは、初心者によくあることです。
無駄な出費を防ぐために、まずは最低限必要なものだけをそろえ、犬の様子を見ながら必要なものを買い足していくのがおすすめです。
購入する際は、口コミやSNSで「使ってよかったグッズ」など、実体験の声を参考にするとよいでしょう。
一人暮らしで犬を飼うために必要な3つの条件
そもそも、一人暮らしで犬を飼っても大丈夫なのかな?
ここ数年、暮らし方や働き方の変化に伴って、一人暮らしで犬を飼う人が増えてきました。
犬を飼うために必要な「住まい」「お金」「時間」の3つの条件をしっかり整えれば、一人暮らしでも犬を飼うことができます。
住まい:ペット可の住居に住んでいる


犬との暮らしをスタートするには、ペット可の住居に住んでいることが大前提です。
ペットと一緒に暮らせるお部屋を探す際は、アパマンショップなどの賃貸物件サイトを利用するのがおすすめです。
検索条件で「ペット可」などのフィルターをかけると、効率的に探せます。
\ペット可賃貸を今すぐチェック!/
▼ペット可賃貸物件探しのポイントと注意点については、以下の記事で詳しく解説しています。


お金:飼育費用を負担できる


犬を飼うためには、初期費用だけでなく「生涯でかかる飼育費用」があることも忘れてはいけません。
一人暮らしの場合は、すべての費用を自分でまかなうことになるため、事前にしっかりとイメージしておくことが大切です。
時間:犬の世話をする時間がある


一人暮らしで犬を飼う場合、多くの人が不安に思うのが「犬の世話をする時間を確保できるのか」です。
犬種や年齢、性格などによって必要な手間は異なりますが、毎日1〜2時間あれば、十分に愛情を注いで世話をすることができます。


まとめ
犬を飼うために必要な初期費用はさまざまあり、入手方法によって総額は大きく変わります。
| 項目 | 金額の目安 | 備考 |
|---|---|---|
| 生体購入 | 0〜50万円程度 | 入手方法で異なる |
| 飼育グッズ | 3万~4万円前後 | フード、トイレ用品など |
| 畜犬登録 | 約3千円程度 | 義務がある |
| 狂犬病 ワクチン接種 | 約3千~4千円 | 接種義務がある |
| 混合ワクチン | 1回あたり 約5千~1万2千円 | 種類で異なる |
| マイクロチップ 装着・登録 | 約3千~1万円 | 義務がある※ |
| 初期費用の合計 | 約4万4千〜56万7千円 | ー |
「どこにお金をかけて、どこで工夫するのか?」を見極めて、しっかりと予算計画を立てれば、一人暮らしの限られた収入でも犬を飼うことができます。
最後までご覧いただき、ありがとうございました。
この記事が、ご参考になれば嬉しいです。
当ブログを通して、みなさんのシングルライフがわんちゃんとのワンダフルライフになれば幸いです。
引用・参考元
- 厚生労働省「犬の鑑札、注射済票について」:https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou10/10.html
- マイクロチップ情報登録制度:https://reg.mc.env.go.jp/owner/microchip_registration_system
- 一般社団法人ペットフード協会「令和5年 全国犬猫飼育実態調査」:https://petfood.or.jp/data-chart/